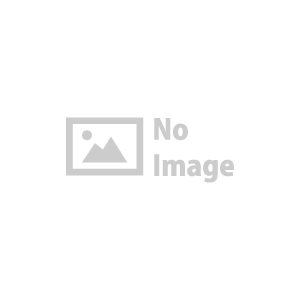
事業場外みなし労働時間制について
専門情報導入するにあたり、気をつけるこのはありますか? 以下の点に気をつけてください。 ①使用者の具体的な指揮監督:及ばないこと②労働時間の算定:困難であること③事業場外の業務に通常必要な時間:適切に設定すること④制度の対象者:事業場外で業務を行う部署または従業員 ※事務職など労働時間の把握ができる部署または従業員は対象外⑤就業規則:規定として、制度を導入すること⑥対象となる従業員に行うこと:説明をすること ⑦事業場外の業務に通常必要な時間が法定労働時間(1日8時間)超える場合:労使協定を締結すること …など ※法定労働時間を超えない場合も労使協定を締結することをお勧めします。 1日の一部だけ事業場外みなし労働時間制を適用できますか? 可能です。ただし、労使協定で『事業場外の業務において通常必要とされる時間』を定める必要があります。 ※『事業場外みなし労働時間制で労使協定を結んだ時間』(1日単位)が法定労働時間を超えない場合、労働基準監督署への届出は必要ありません。 企業内で一部勤務している時間を、事業場外みなし労働に含めることができますか? 【原則】事業場外みなし労働時間制を利用し、企業内で一部勤務をしている場合 ▶『所定労働時間内の労働』として取り扱う。 【例外】『事業場外の労働時間』と『事業場内の労働時間』をあわせて所定労働時間を超える場合 ▶労働時間は? 注意点 企業は労働契約の締結の際、労働条件を原則として書面で通知しなければなりません。 ※労働条件通知書には、適用される始業時刻と終業時刻を記載します。 続きを読む




